「生まれてきて良かった」と,
子どもに思わせたい。
引用元:『本・子ども・絵本』中川李枝子 著 帯
この帯に使われている言葉を見るだけで,思わず手にとってしまいたくなる本だが,内容が本当にすばらしい。幼少の頃の戦争体験から保育園で保母さんをしていた実体験,絵本作家,児童文学作家になった経緯まで,自身の半生と【本・子ども・絵本】がどう関わってきたのか。いかにその3つは大切だったのか。そんなことを教えてもらえる本であると同時に,自分と【本・子ども・絵本】はどうだろうと考えずにはいられなくなる。
そして,もっと【本・子ども・絵本】との関わりを大事にしようと思えてくる。この3つを大事にすることで子育てが劇的に変わるような気さえしてくる。そんな素敵な本である。
それと,引用した言葉は,映画『崖の上のポニョ』のキャッチコピーである【生まれてきて,よかった】を思わせる。
宮崎駿監督が作品に込める【この世は生きるに値する】というテーマをも思わせる。自分の子どもにも思ってもらいたい。【生きていてよかった】とか【生まれてきてよかった】とか。
児童文学の本質は,そこにある。だからこそ,今,親になって児童文学に触れてみているわけだが,この『本・子ども・絵本』を読むことでさらに,児童文学や絵本について知りたくなり,自分の人生に取り入れたくなってくるはずだ。
宮崎駿監督が尊敬する中川李枝子さん
ぼくが,この本を読むことになったのは,アニメ界の巨匠,宮崎駿監督がきっかけだった。以前,紹介した書籍『本へのとびらー岩波少年文庫を語る』で,中川李枝子さんについて触れられていたからだ。
中川李枝子さんは,もともとは保育園で働く保母さんで,その経験を生かして絵本・児童文学作家になった人だ。代表作『ぐりとぐら』は,あまりにも有名。
宮崎駿監督は,自身の書籍で,中川李枝子さんについて,児童文学の翻訳家である石井桃子さんと同様に,別格の大先輩として名を挙げている。
子どもたちにとっての遊びの世界って,現実と空想の境目がないんですよ。空間にも時間にも束縛されていません。中川李枝子さんは,それをそのまま受け止めて,そのまま書ける人なんです。
『本へのとびらー岩波少年文庫を語る』 宮崎駿 著 自分の一冊にめぐり合う
中川李枝子さんの作品『いやいやえん』という児童文学作品についても,以下のように書かれている。
別格ということでは,中川李枝子さんもそうです。
なかでも一番衝撃を受けたのは,『いやいやえん』です。これは学生時代に読んだのですが,「ついてに出た」というふうに思いました。(中略)この作品の何がすごいかって,子どもも気づかない子どものことが書いてあることです。
『本へのとびらー岩波少年文庫を語る』 宮崎駿 著 自分の一冊にめぐり合う

あの宮崎駿をして,ここまで言わしめる中川李枝子さんとは一体何者だ!!
絵本のことも,児童文学のことも,全然興味もなく,知らなかった自分としては,この育休期間を機に,中川李枝子さんの書籍や作品を読もう!と決意したのだった。
誤解を恐れずにいうと,正直,絵本は「子ども向け」であり,子どもが読むもので,幼稚なものと決めつけていたところがあった。親になり,絵本に触れることでその考えは,真逆なものとなった。

相手が子どもだからこそ,全力で,まっすぐに,正直に,自分よりも下だと思わずに,関わらなければならない!
きっと,ジブリ作品も,中川さんの絵本も,子ども相手だからこそ,真剣に,本気で作品を作られているのだろうと。
宮崎駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』の主題歌を担当した米津玄師さんも子どもが相手だからこそ手を抜かないという思いで『地球儀』を作ったと語っていた。それも当然,宮崎駿監督の影響だそうだ。
『本・子ども・絵本』の概要
この本の前半は,【子どもと絵本】【母と子の絵本の時間】など,絵本が育児・子育てをより良いものにしてくれることが語られる。実際に,母親として,保母さんとしてどのような絵本とともに育児や保育をしたか,具体的に書かれていて,紹介されている絵本は全部欲しくなってしまう…。
後半からは,中川さんが幼少の頃,どれだけ本が貴重なものであったか,それをどう手に入れ,家族で共有していたか,本や児童文学が中川さんという一人の人間をかたちづくる大きな要因になったことがよくわかる内容となっている。また,当時,戦時中ということもあり,いかに本や絵本が貴重なものであったかもよくわかる。
読書の入り口である絵本はまた,人生の入り口のような気がします。
なぜなら,生きることは素晴らしいと,子どもひとりひとりにしっかりおぼえこませるチャンスだからです。
『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著
本書を通して,きっと,絵本や児童書が子どもの人生を豊かにしてくれるに違いないと確信できると思う。
絵本や児童書から,世界のやさしさ,きびしさ,空想する力,判断する力,すなわちこの世界を学ぶ。
それを与えるのは,親の責任だろうと思う。
内容(「BOOK」データベースより)
物心つく頃から本に夢中になり、沢山の本を読んで育った著者。長年務めた保育士時代は、子ども達に絵本の読み聞かせをした。「本は子どもに人生への希望と自信を与える」と信じる著者が、信頼を寄せる絵本や児童書を紹介し、子どもへの向き合い方などアドヴァイスを綴る。『ぐりとぐら』の作者が贈る名エッセイ。絵本30冊&児童書58冊を紹介!
育児初心者,育休をとったパパなどにおすすめしたい本。引用したい言葉だらけではあるが,自分が育休中の父親であることと2児の父親であることを視点に,6つほど激選してこの本の魅力を伝えていきたい。
このブログは,あくまでも読書感想で,誤った解釈をしている可能性があります。本を読んで今の自分が感じたこと,考えたことを書くに過ぎないので,本書の解説文でもなければ,要約でもありませんのご注意を。
心を落ち着かせてくれる絵本
絵本を読む時間は,一日のなかでいちばん落ち着く,気持ちがおだやかになる貴重なひとときでした。絵本を読みながら子どもひとりひとりをしみじみと眺め,心の底から,ああ何て良い子だろう,可愛いんだろうと感じ入り,ついさっきまで,この子たちに腹を立てたり叱ったりしていたことが恥ずかしくなって,そのぶんだけでもやさしくしなくてはーと反省するのでした。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 子どもと絵本
絵本を子どもと一緒に読んでいるときって,たしかに落ち着く。ゆっくりと時間が流れ,ゆったりとした空間になる。
ぼくは,寝る前に2,3冊ほど子どもと絵本を読むのだが,早く寝てほしいときに,急ぎ足で読んでしまうことがある。これはよくないと反省。
寝る前に,絵本の世界に旅立ってもらい,日常から離れた時間と空間の中を過ごしてもらい,心をやわらげ,一日を気持ちよく終えるのもいいなと思った。
子どものことを教えてくれる絵本
絵本を見るとき,子どもが何気なく口にする言葉,物語や絵への関心ぶり,反応などから,その子の性格や育ち方をのぞき見ることができます。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 子どもと絵本
これは,中川李枝子さんが保育士として子どもを見ていたときのことでもあるが,わが子だとどうだろう。
落ち着いて絵本を読めないときは,もしかしたら,その日いやなことがあったのかもしれないし,おなかがすいているのかもしれないし,心配なことがあるのかもしれない。単純に眠いだけかもしれない。
少なくとも,【いつもとはちがう】ということもわかるのかもしれない。そうしたバロメーターにもなるのかもしれない。
ただ,絵本を一緒に読みながら,反応を見ているとおもしろい。子どもが何をおもしろいと感じたり,こわいと感じるのか,がよくわかる。
そうして,わが子を知ることもひとつなのかもしれない。
世界を広げてくれる絵本
子どもは絵本を見るとき,身を乗り出してきます。まさに遊ぶときと同じ,絵本の世界に身も心も入っていく感じです。そうして,絵本の中で主人公と一体になってさまざまな体験をします。それは心の体験と呼ばれますが,現実ではとても味わえないことを想像で味わうのです。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著
え!それどこで覚えた言葉!?とか,なんでそんなこと知ってるの!?ということは,だいたい絵本から学んだことのような気がする。
それをごっこ遊びにも取り入れたりして,子どもの遊びの世界には限りがないなと感じたりもする。
宮崎駿は,❝子どもたちにとっての遊びの世界って,現実と空想の境目がないんですよ。空間にも時間にも束縛されていません。❞ということを『本へのとびらー岩波少年文庫を語る』で語っている。
現実で味わえないことを絵本を通して想像の世界で味わい,それを現実に持ち込んで,自分の生きる力にかえているような気がする。
自分の子どもの頃を思い出すと,そうだったのかもと思い当たることもある。絵本の思い出は数冊しかないが,テレビアニメはよく見ていた。自分が主人公のつもりだった。
たいせつなこと,教訓のようなものって,絵本やアニメ,漫画のような創作からなんとなく知った気になって,現実に起きる実体験を伴って自分のものになる。
ともすれば,できる限り良いものと出会わせたい。特に幼少期に。
与えすぎ現金!子どもの時間・空間の流れ方
想像力と創造力で,子どもの生活は活気にみちています。まさに退屈知らず,あわてて新しいものに飛びつかなくていいのです。子どもたちは何事にも,あわてず,ゆっくり吟味する余裕を持ってのぞみます。それは成長のとても大切な過程ではないでしょうか。
新しいものをどんどん与えると,吟味する時間が失われ,大事な能力を弱めてしまうでしょう。
絵本に関しても同じことがいえます。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 母と子の絵本の時間
【想像と創造】いつ失った力かわからないが,大人の大半はいつからか,どこからかこの力を失ったのだと思う。
いかに,自らの暇と退屈を商業的なエンターテイメントで浪費させられているか,考えると恐ろしくなる。
子どもは違う。そもそも時間なんてどうでもいい。自らの頭や心の中に広がり続ける世界を泳いでいる。
そうか,新しいものを与えると,そういった大事な力が失われてしまうのか。
親である自分が,あのおもちゃはおもしろくないとか,すぐ飽きるとかで,すぐに新しいものを買い与えるから,主体性を失い,想像力も創造力もなくなってしまうのか。
この言葉に出会えてよかった。
冒険に連れていってくれる絵本
遊びながら育つ時代,子どもの心は本当に自由で,いつも無限に広がる世界に身を置き,創造力を働かせ,ありとあらゆる冒険をこころみます。毎日が愉快でたまらないのは当然,寝るのを泣いていやがるはずです。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 みどり保育園のこと
どんな親もなるべく早く寝かしつけたい,と思っているはず。ぼくもそう。だって,早く寝てくれないと,次の日の朝,自分から起きてくれなくて,その結果,朝の準備も遅くなる。「早く朝ごはん食べて」とか「早く顔洗って!」などと言いたくないことを言わなければならなくなり,機嫌の悪い子どもと対峙しなくてはいけない。本当に嫌だ。
ただ,そうか。満足に遊んで寝ることも必要だなと思った。理想的なのは,満足に食べること。満足に遊ぶこと。満足な睡眠時間を確保すること。この3つがしっかりできたら,きっと気持ちよく過ごせるのだろう。
それはそうだよねと思う。だって,せっかく未知の世界への大冒険に旅立っているのに,横から親が,「早くお風呂入りなさい!」なんて言うと,それどころじゃない!となる。
冒険,旅の邪魔をしてはいけない。
そうはいっても,戻ってきてもらわないといけないから,うまく時間のコントロールをしてあげないといけない。親が。
我が家では,14時30分には幼稚園から帰ってくる。17時前までは,遊ぶ。公園に行くか,お絵描きをするか,積み木で遊ぶか,ママと料理をするか,その間におやつタイムもある。17時からは夕食。18時までにはお風呂に入り始める。18時30分には,お風呂から出て19時30分まではまた遊ぶ。19時30分から20時までの間に寝室へ行き絵本を読んで寝る。そうすると,朝7時までには自分で起きてくれる。朝,どうしても機嫌が悪いことはあるけれど,幼稚園に行きたくないと言ったことはない。ある程度は,満足させられているのだろうか。
子どもをひとりの人間として知る
その子にとって,今いちばん大切なこと,必要なことは何か,がわかるのは,お母さんです。他人を当てにしないで,自分の頭と心で子どもに向かいあい,余計な騒音にはひきずりこまれないでほしい。これはお母さんだけのことだけではなく,お父さんも同じです。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 みどり保育園のこと
こわいのは,分かった気になるということ。いくら自分の子どもだからといって,すべてが分かるわけじゃない。それなのに,親だからという理由で自分の子はこんな子と決めつけてしまうことがこわい。
期待しすぎてもダメ。自分が望んだ子になる必要はないから。親の期待通りの人生を歩む必要はない。
ときれいごとを言っても,無意識にそう仕向ける親はいくらでもいる。
「わが子はこんな子」を決め込んでしまうことで,本当にそうなってしまう。それが,子どもにとって良いか悪いかはその時には分からない。
だから,気をつけておくべきなのは,それが子どものことを一番に考えてしている行動なのかということ。
自分本位になっていないか。常に考えておかないと,どうしても思い通りにしようとしてしまう。
子どもの心に寄り添うとか,心の声をきくとか,なかなかできることではないけれど,自分の子にとって何がいちばんか,常に考えていたい。
生きていく力を育んでくれる絵本
絵本は幼児の成長の糧となる遊びを豊かに育てます。
絵本は,読書の入り口といわれ,人生の入り口のような要素を持っています。
引用元:『本・子ども・絵本』 中川李枝子 著 あとがき
絵本は,しょせん「子ども向け」。だから,劣っている,理解できなくてもいい,というようなことを思っていた。そんなことはない。真逆である。
❝子ども向けだからこそ最高のものを…❞とは,おもちゃデザイナーの相沢康夫さんの言葉であるが,【子どもとは大きな可能性を秘めている人類の宝】
その宝に対するものが【子ども向け】の絵本だったり,児童書であるわけなので,最高のものでなければならない!といえると思う。
絵本や児童書が,成長の糧となる遊びを豊かにする。
子どもは遊びの中で,学ぶ。砂や葉っぱなどふれたものの肌触りを確かめて水を流したり掬ったりして理科をする,おままごとや料理のごっこ遊びで家庭科をする,数を分けたり合わせたりして算数をする,お話をしたり,聞いたりして国語をする。
その入り口が絵本であるということだ。
絵本の世界には限りがない。その中で,子どもたちは,大人が想像もしていないこと学ぶ,そして大人の想像を超える発想をもとに遊び,学ぶ。
どんなに時間がなくなっても,絵本を読む時間を確保し,落ち着いた時間を過ごすとともに,子どもの状態を確かめ,冒険の世界に旅立ってもらう毎日を送ろう。
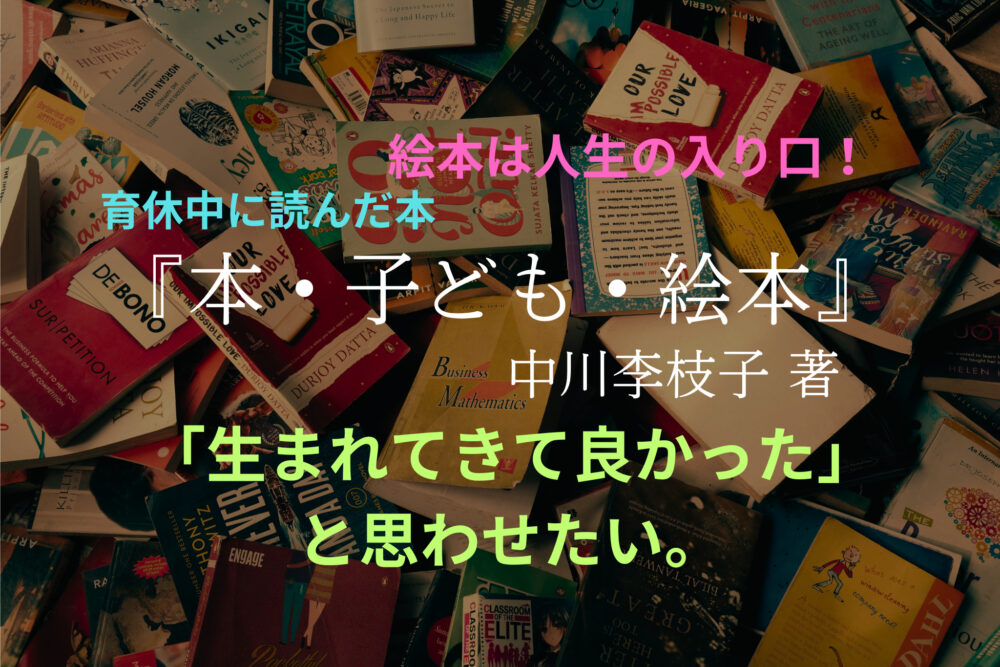
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33d7a86a.f0ffa8bf.33d7a86b.6f5d4558/?me_id=1213310&item_id=19363438&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2000%2F9784167912000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


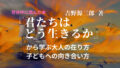
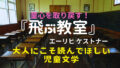
コメント